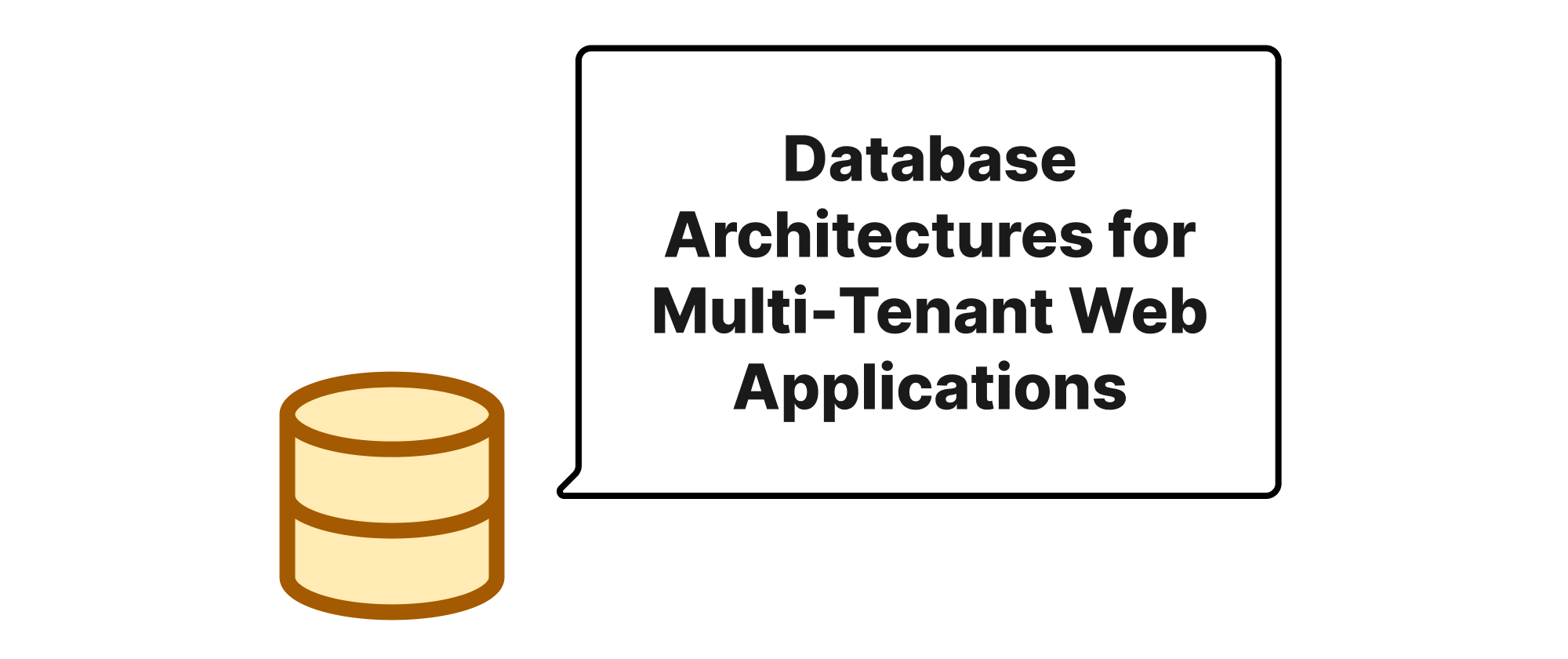データベースレプリケーションによる読み取りと書き込みのスケーリング
Daniel Hayes
Full-Stack Engineer · Leapcell
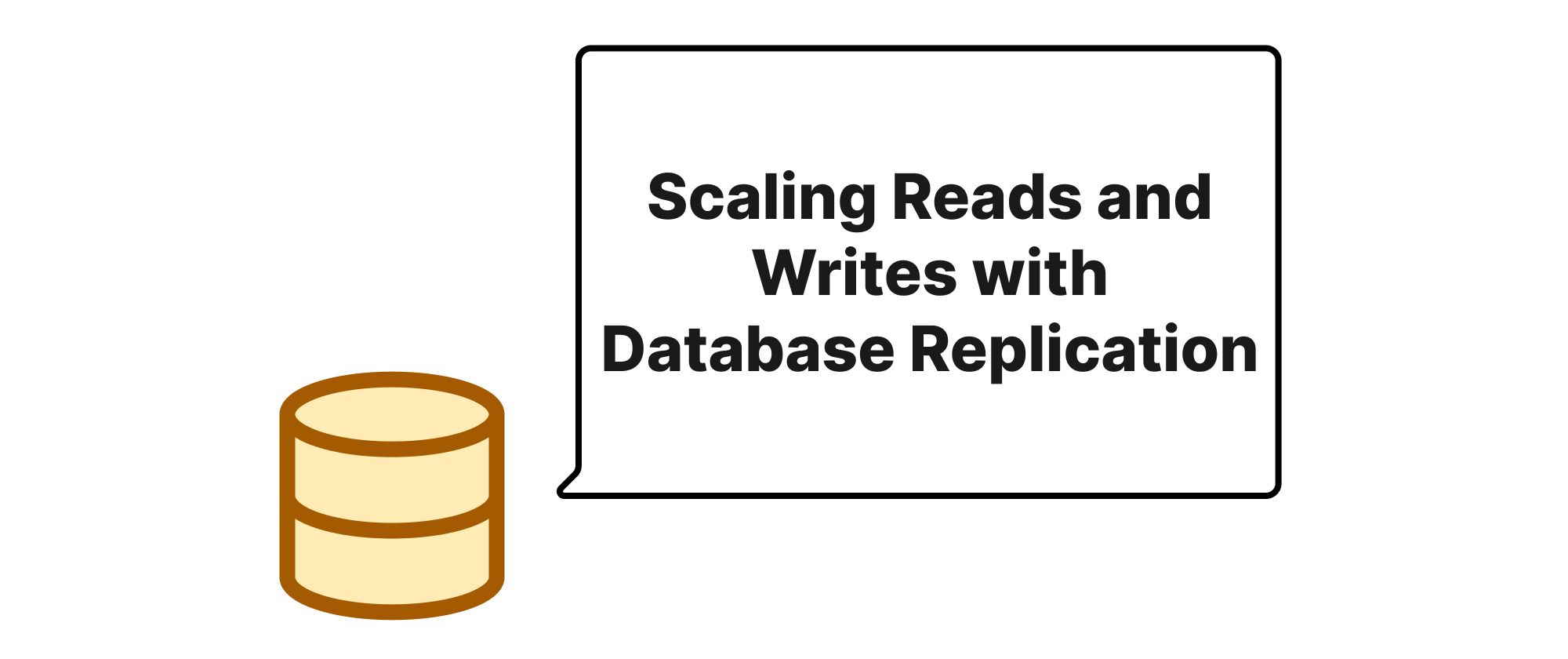
はじめに
今日のデータ駆動型の世界では、アプリケーションは高いパフォーマンスと可用性を要求します。ユーザーベースの成長とデータ量の爆発的な増加に伴い、単一のデータベースインスタンスではしばしばボトルネックとなります。特に書き込みと同じリソースにアクセスしようとする読み取り負荷が高い場合、パフォーマンスの問題は応答時間の遅延やユーザーエクスペリエンスの低下につながる可能性があります。この課題は、スケーラブルなデータベースアーキテクチャの重要な必要性を浮き彫りにします。これらの制限を克服するための強力で広く採用されているソリューションの1つは、データベースマスター・レプリカレプリケーションを活用した**読み書きの分離(read-write splitting)**です。このアプローチは、アプリケーションのスループットを高めるだけでなく、その耐障害性も強化し、最新の分散システムの基盤となっています。
データベーススケーリングのコアコンセプト
読み書きの分離の詳細に入る前に、このアーキテクチャパターンを支えるいくつかの基本概念を理解しましょう。
-
レプリケーション: 中核となるレプリケーションは、データの複数のコピーを作成し、維持するプロセスです。データベースでは、これは通常、プライマリ(マスター)データベースから1つ以上のセカンダリ(レプリカまたはスレーブ)データベースにデータをコピーすることを含みます。主な目的は、データの冗長性を確保し、可用性を向上させ、ワークロードを分散することです。
-
マスター(プライマリ)データベース: これは、すべての書き込み操作(INSERT、UPDATE、DELETE)を受け付ける権限のあるデータベースインスタンスです。読み取り操作を処理することも可能ですが、読み書きの分離設定では、読み取りは主にレプリカにオフロードされます。
-
レプリカ(スレーブ)データベース: レプリカデータベースは、マスターのデータのコピーを保持しています。通常、読み取り操作のみを処理するように構成されています。レプリカはマスターから非同期に変更を受信して適用し、可能な限り最新の状態を保つよう努めます。
-
非同期レプリケーション: 非同期レプリケーションでは、マスターデータベースはトランザクションをコミットしてから、変更をレプリカに送信します。マスターは、自身のトランザクションをコミットする前に、レプリカが変更の受信または適用を認識するのを待ちません。これにより、マスターでのパフォーマンスは高くなりますが、マスターとレプリカの間でわずかな遅延(レプリケーションラグ)が発生する可能性があります。ほとんどのマスター・レプリカ設定では、非同期レプリケーションが使用されます。
-
読み書きの分離(Read-Write Splitting): これは、アプリケーションがすべての書き込み操作をマスターデータベースにルーティングし、読み取り操作を1つ以上のレプリカデータベースに分散するアーキテクチャパターンです。この懸念事項の分離により、マスターは読み取りクエリからの競合なしに効率的に書き込みを処理でき、レプリカは多数の読み取りを同時に提供できます。
読み書きの分離の原則と実装
マスター・レプリカレプリケーションによる読み書きの分離の基本的な原則は、データベース操作をその影響度に基づいて分離することです。書き込みはデータを変更し、読み取りはデータの取得のみを行います。マスターを書き込みに、レプリカを読み取りに専念させることで、システムはより大きなスケーラビリティとパフォーマンスを実現できます。
仕組み
- 書き込み操作: すべての
INSERT、UPDATE、DELETEクエリはマスターデータベースにルーティングされます。マスターはこれらのトランザクションを処理し、データを更新し、バイナリログ(MySQLではbinlog)またはトランザクションログ(PostgreSQLではWAL)に変更を記録します。 - レプリケーション: レプリカはマスターのトランザクションログを継続的に監視します。新しい変更が検出されると、これらの変更を取得し、ローカルのデータコピーに適用して、マスターとの最終的な整合性を確保します。
- 読み取り操作: すべての
SELECTクエリは、1つ以上のレプリカデータベースにルーティングされます。これにより、マスターへの読み取り負荷がオフロードされ、マスターが書き込みトランザクションに集中できるようになります。ロードバランサーまたはアプリケーションレベルのルーティングメカニズムが、これらの読み取りクエリを利用可能なレプリカに分散します。
実装戦略
読み書きの分離の実装には、通常、アプリケーションレイヤー、データベースプロキシレイヤー、またはその両方の組み合わせでの変更が必要です。
1. アプリケーションレベルのルーティング
このアプローチでは、アプリケーションコード自体が、クエリが読み取りか書き込みかを判断し、適切なデータベースインスタンスに接続する責任を負います。
例(架空のPython/SQLAlchemyセットアップを使用):
from sqlalchemy import create_engine, text from sqlalchemy.orm import sessionmaker # データベース接続文字列 MASTER_DB_URL = "mysql+mysqlconnector://user:password@master_host/db_name" REPLICA_DB_URL = "mysql+mysqlconnector://user:password@replica_host/db_name" # エンジンの作成 master_engine = create_engine(MASTER_DB_URL) replica_engine = create_engine(REPLICA_DB_URL) SessionLocal = sessionmaker(autocommit=False, autoflush=False) def get_db_session(write_operation: bool): """ マスターまたはレプリカに接続されたSQLAlchemyセッションを返します。 """ if write_operation: SessionLocal.configure(bind=master_engine) else: # 複数のレプリカ間のロードバランシングのためのロジックを追加する可能性があります SessionLocal.configure(bind=replica_engine) session = SessionLocal() try: yield session finally: session.close() # Webアプリケーションコンテキストでの使用: def create_new_user(user_data): with next(get_db_session(write_operation=True)) as db: db.execute(text("INSERT INTO users (name, email) VALUES (:name, :email)"), user_data) db.commit() return {"message": "User created successfully"} def get_user_by_id(user_id): with next(get_db_session(write_operation=False)) as db: user = db.execute(text("SELECT * FROM users WHERE id = :id"), {"id": user_id}).fetchone() return user
長所: 最大限の柔軟性、ルーティングに関するきめ細かな制御。 短所: 大幅なアプリケーションコードの変更が必要、ルーティングにおける開発者のエラーの可能性、複数のデータベース接続の管理が複雑になる可能性がある。
2. データベースプロキシレベル
より一般的で、しばしば好まれるアプローチは、データベースプロキシを使用することです。プロキシは、アプリケーションとデータベースインスタンス間の仲介者として機能します。受信したクエリをインターセプトし、それらを検査し、設定されたルール(例:クエリタイプ、SQLキーワード)に基づいてマスターまたはレプリカにルーティングします。一般的なプロキシソリューションには、MaxScale(MySQL用)、PgBouncer(PostgreSQL用、ただし主にコネクションプーラーですが、ルーティング用に拡張可能)、および独自ソリューションが含まれます。
例(概念的なMaxScale設定スニペット):
[master_server] type=server address=192.168.1.10 port=3306 protocol=MySQLBackend [replica_server_1] type=server address=192.168.1.11 port=3306 protocol=MySQLBackend [replica_server_2] type=server address=192.168.1.12 port=3306 protocol=MySQLBackend [readwritesplit_service] type=service router=readwritesplit servers=master_server,replica_server_1,replica_server_2 router_options=master=master_server # MaxScaleはクエリを自動的に分析して、書き込みをマスターに、読み取りをレプリカにルーティングします。 # 複数のレプリカ間での読み取りロードバランシングも処理できます。 [readwritesplit_listener] type=listener service=readwritesplit_service protocol=MySQLClient port=4006
この設定では、アプリケーションはプロキシのリスナーポート(例:4006)にのみ接続し、プロキシが透過的にルーティングを処理します。
長所: アプリケーションコードはほとんど変更されない、ルーティングルールの集中管理、堅牢なロードバランシング機能、アプリケーションの接続管理を簡素化する。 短所: 追加のレイヤーの複雑さと潜在的な単一障害点(ただし、プロキシは高可用性も実現可能)。
主要な考慮事項
- レプリケーションラグ: 非同期レプリケーションは、マスターとレプリカの間に遅延を導入します。アプリケーションはこれを認識する必要があります。たとえば、ユーザーがマスターにデータを書き込み、すぐにレプリカからそれを読み取ろうとした場合、データがまだレプリカで利用可能になっていない可能性があり、「古い読み取り」につながる可能性があります。これを軽減する戦略には以下が含まれます:
- 書き込み後の読み取り整合性: 書き込み直後の重要な読み取りについては、マスターに読み取りを指示します。
- レプリケーションの待机: 場合によっては、アプリケーションが読み取りを実行する前に、特定のトランザクションIDまでレプリカが追いつくのを明示的に待機することがあります。
- 最終整合性の許容: 比較的重要でないデータについては、わずかな遅延を許容することがしばしば可能です。
- ロードバランシング: 複数のレプリカがある場合、ロードバランサー(外部システムまたはデータベースプロキシに組み込まれたもの)は、レプリカ全体に読み取りクエリを均等に分散し、単一のレプリカがボトルネックになるのを防ぐために不可欠です。
- フェイルオーバー: マスターが失敗した場合はどうなりますか?堅牢な設定には、レプリカの1つを新しいマスターに昇格させるための自動または手動フェイルオーバーメカニズムが含まれます。これにより、高可用性が保証されます。
- 監視: すべてのデータベースインスタンスのレプリケーションステータス、レプリケーションラグ、およびリソース使用率(CPU、メモリ、I/O)を綿密に監視し、問題をプロアクティブに特定して対処します。
結論
データベースマスター・レプリカレプリケーションと読み書きの分離は、スケーラブルで回復力のあるアプリケーションを構築するための不可欠なアーキテクチャパターンです。書き込み操作と読み取り操作をインテリジェントに分離することで、データベースのパフォーマンスを大幅に向上させ、プライマリインスタンスへの負荷を軽減し、システム全体の可用性を向上させます。レプリケーションラグやフェイルオーバーなどの考慮事項には注意が必要ですが、スループットと応答性の向上というメリットにより、このアプローチは最新のデータ集約型システムにとって最適なソリューションとなり、アプリケーションがますます増加する要求にスムーズに対応できるようになります。この戦略は、単一のデータベースボトルネックを、膨大な負荷を処理できる分散型パワフルシステムへと変革します。